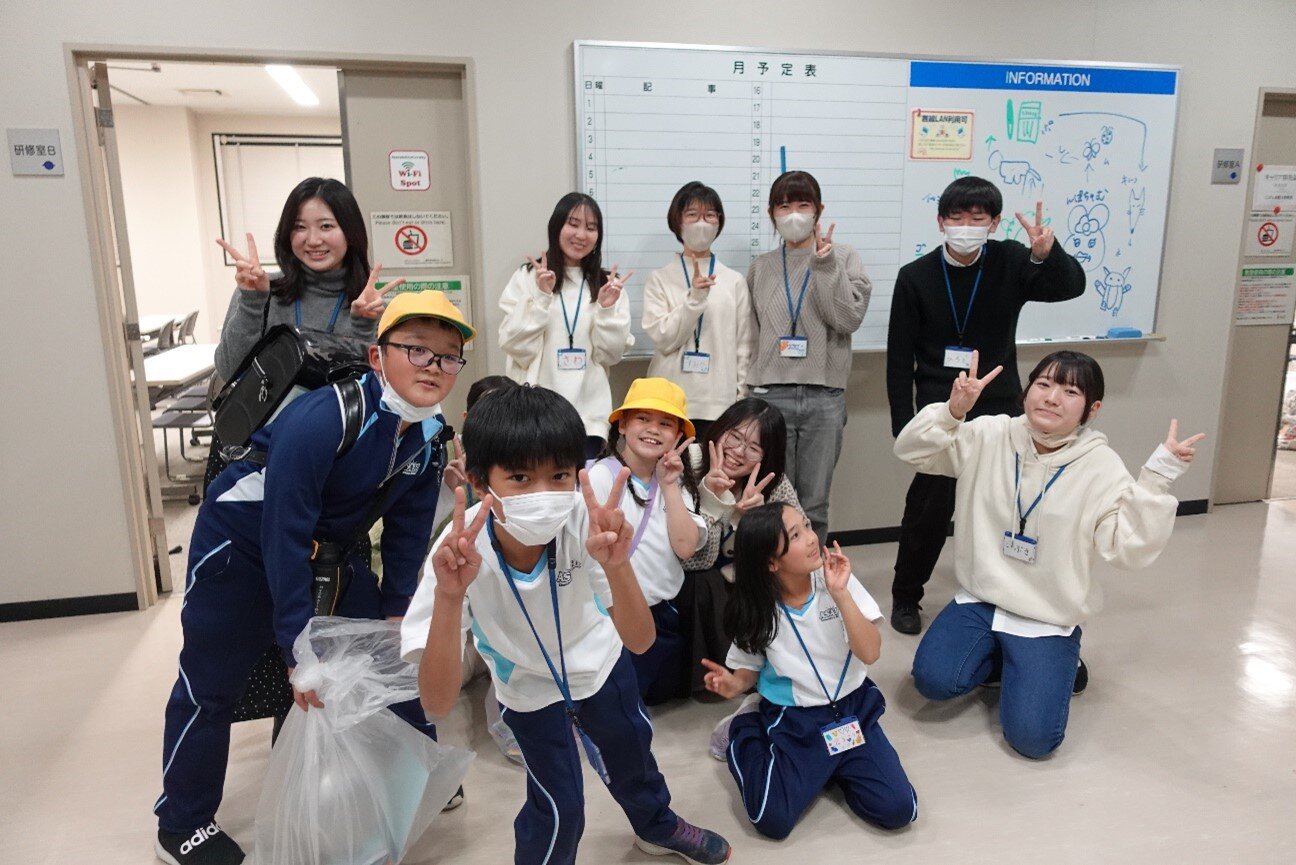「耕さない農業」に気候変動を抑える効果!?
- 2022年12月20日
-
- 研究
- 農学部

農業といえば「耕す」というイメージが強いだけに、「耕さない農業」と聞くとちょっと不思議な感じがするかも知れません。しかし、茨城大学農学部の附属農場である国際フィールド農学センターでの長年の実証実験からは、「耕さない農業」が、地球温暖化の原因となる炭素を土の中に留め置いたり、土壌の微生物の多様性を高めたりといった点で有効だということがわかってきました。
同センターの小松﨑将一教授らの研究グループは、土壌改良のために土を覆うようにして作物を栽培する「カバークロップ」の導入と、不耕起(土を耕さない)の栽培とを組み合わせて、オカボやダイズをつくる実験を、20年という長きにわたって続けています。
その結果、ライ麦によるカバークロップと不耕起栽培との組み合わせによって、土壌の炭素貯留量が増加することがわかりました。土壌の炭素貯留については、空中の大気中の温室効果ガスの削減にもつながるものであり、気候変動の緩和策として注目されるものです。
さらに、土壌微生物のバイオマスに関する指標にも増加が見られました。
これらの結果は、地球温暖化防止や生物多様性保全といった環境に関する課題の解決に貢献する営農活動の可能性を示唆するものといえるでしょう。
担当者
農学部 教授 小松﨑 将一
研究者情報